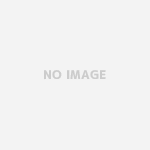金沢の銘菓、きんつばを食べていて、どうして羊羹という甘い小豆のお菓子に、羊という漢字が使われているのか疑問に思い、調べてみました。
寒天を煮溶かして砂糖と餡を加え練り固めた「羊羹」。
羊は、文字通り、「ひつじ」。
羊羹の「羹」は、あつもの、つまり野菜や肉などのスープです。
甘い羊羹と羊の関係は?
つまり羊羹は、もともととろみのある羊肉のスープでした。
中国で禅僧の軽い朝食として食べられていました。
中国では羊は、大切な生き物。
「羹」は、羊と美しいが重なっています。
羊が3つも隠れている羊羹は大切な食べ物だったのでしょう。
さて「羊肉のスープである」羊羹は、鎌倉室町の時代、禅宗文化とともに日本に伝わりました。
食事と食事の間に食べる小食の一つ、点心(てんじん)として。
日本では、その時代、家畜としての羊がいなかったことや、仏教で肉食を禁じていたために、小豆の蒸したものを羊肉に見立ててスープの中に入れました。
後に小豆の蒸したものをそのまま菓子として食べるようになったのが、蒸し羊羹の始まりです。
蒸し羊羹と練り羊羹の違い
蒸し羊羹の作り方
小麦粉が入って加熱します。
練り羊羹の作り方
寒天が入ります。
どうして、1棹(さお)、2棹と数えられるの?
寒天を使った練り羊羹は、日持ちがします。
江戸時代(1800年ごろ)から人気となりました。
また当時、羊羹は長さ6寸(約18センチ)、厚さと幅が1寸(約3センチ)の細長い棒状で売られ、棹物(さおもの)菓子とも呼ばれました。
そのため、今でも、羊羹は、1棹、2棹と棹(さお)で数えられています。